
- イベントレポート
- EC事例から学ぶ!戦略的KPI設計とユーザー軸で考えるWebサイト改善|セミナーレポート
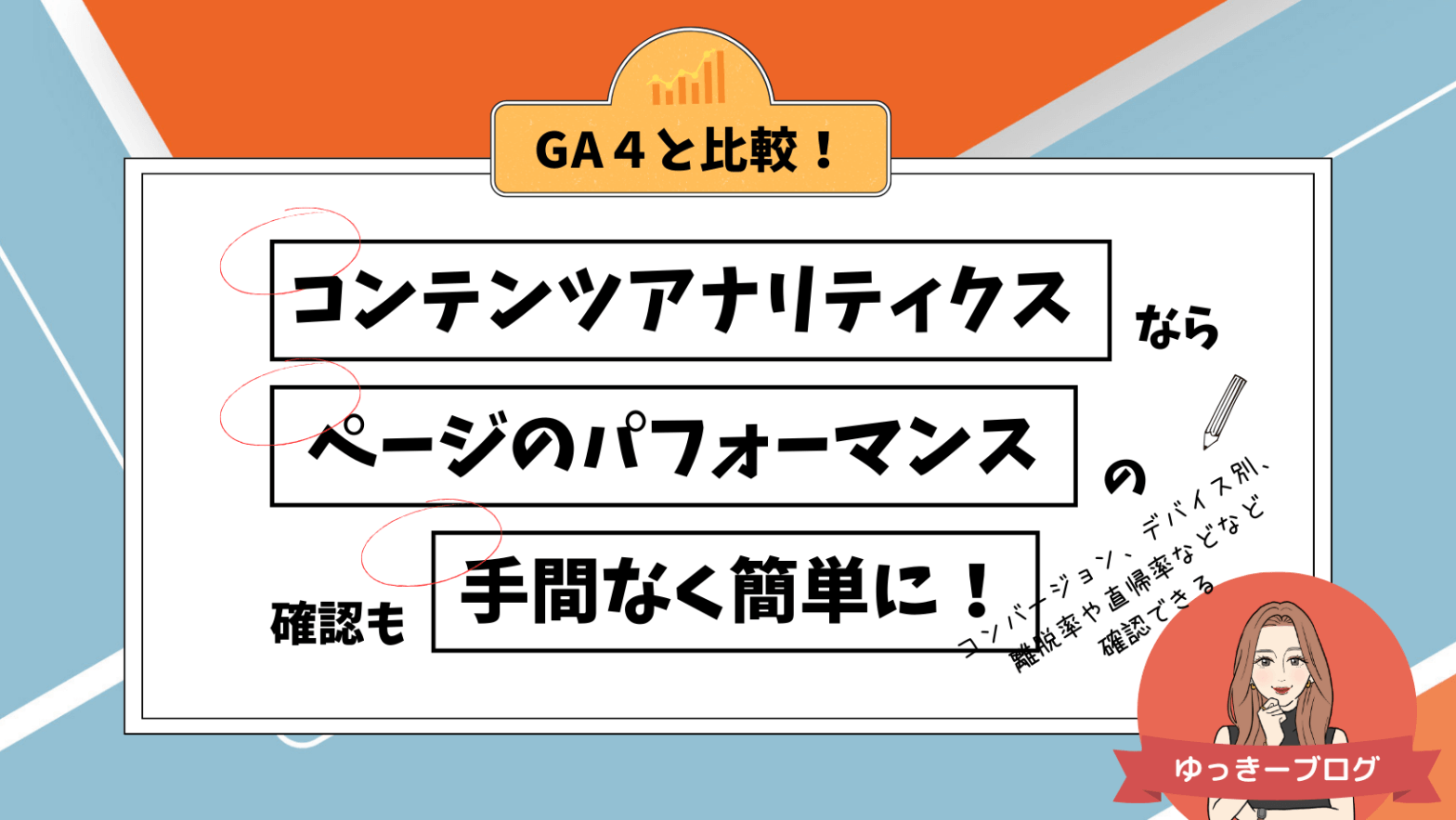
- カスタマーデータ活用
- GA4と比較!コンテンツアナリティクスならページのパフォーマンス(コンバージョン、デバイス別、ディレクトリ別、到達率)の確認も手間なく簡単に!

- カスタマーデータ活用
- 3rd Party Cookie終焉に見るCDP(1st Party Data)の未来|CDP専門書籍の著者COO小畑が解説!
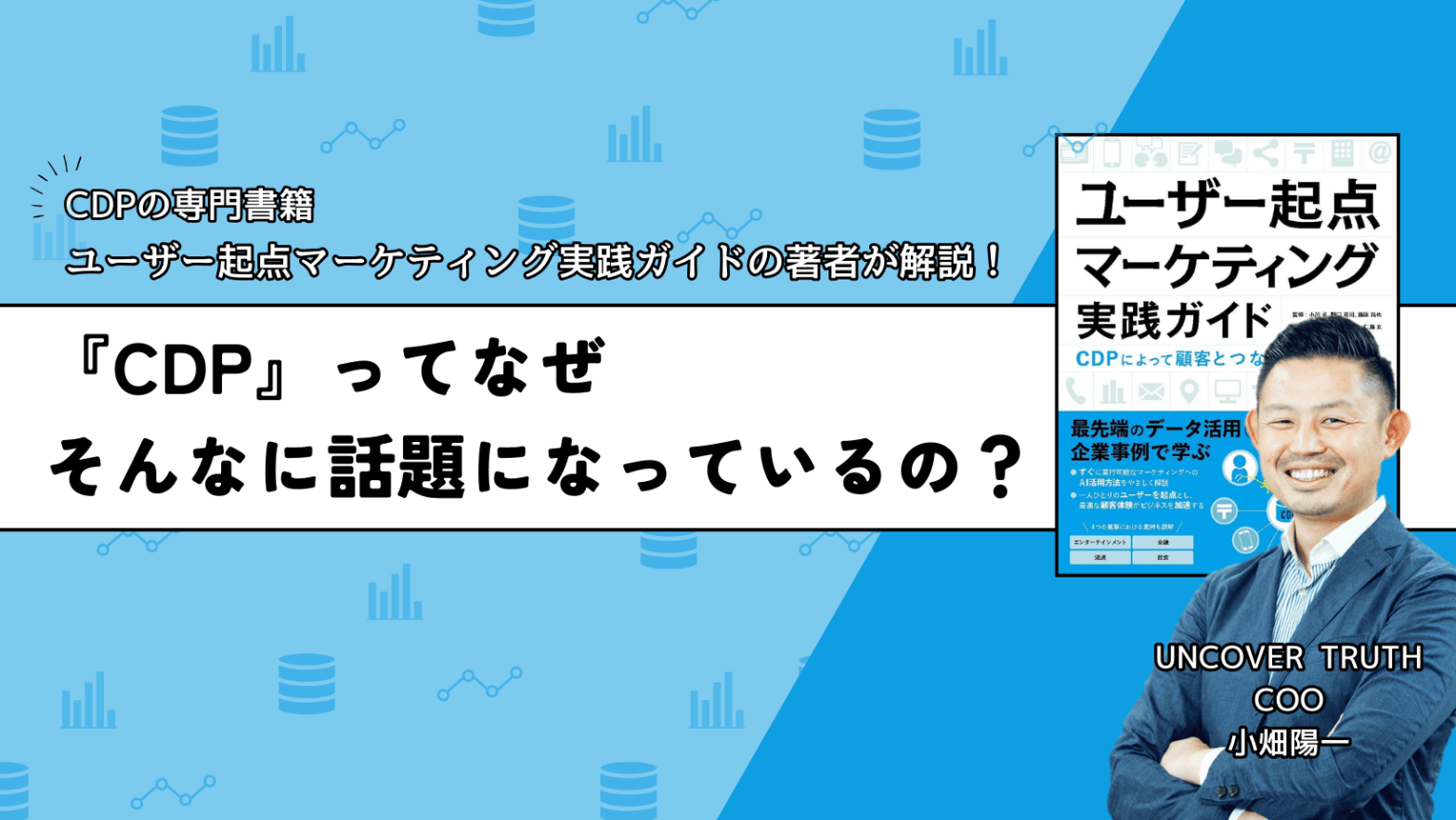
- カスタマーデータ活用
- 『CDP』ってなぜそんなに話題になっているの?|CDP専門書籍の著者COO小畑が解説!
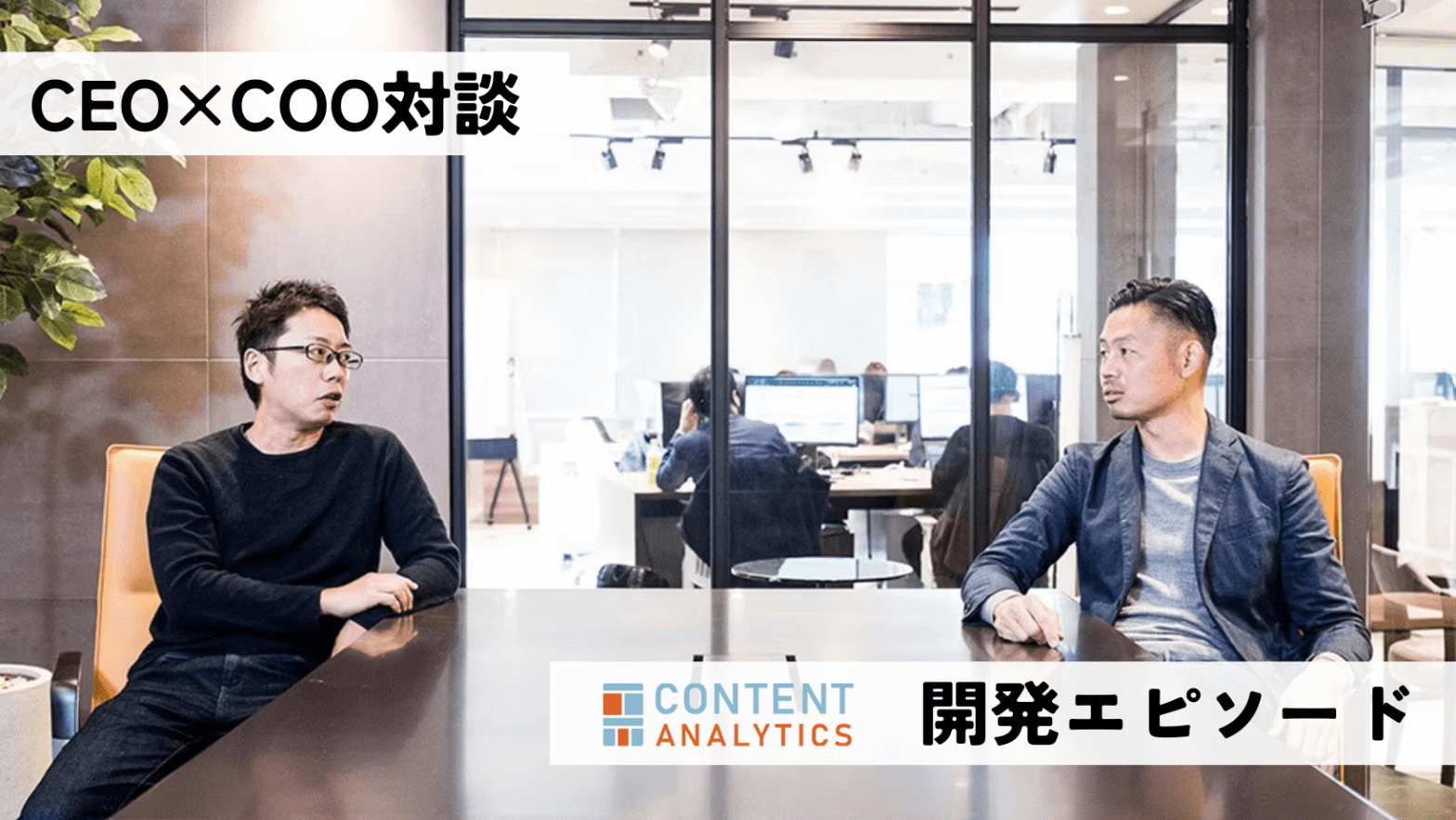
- カスタマーデータ活用
- CEO×COO対談|コンテンツアナリティクス開発エピソード
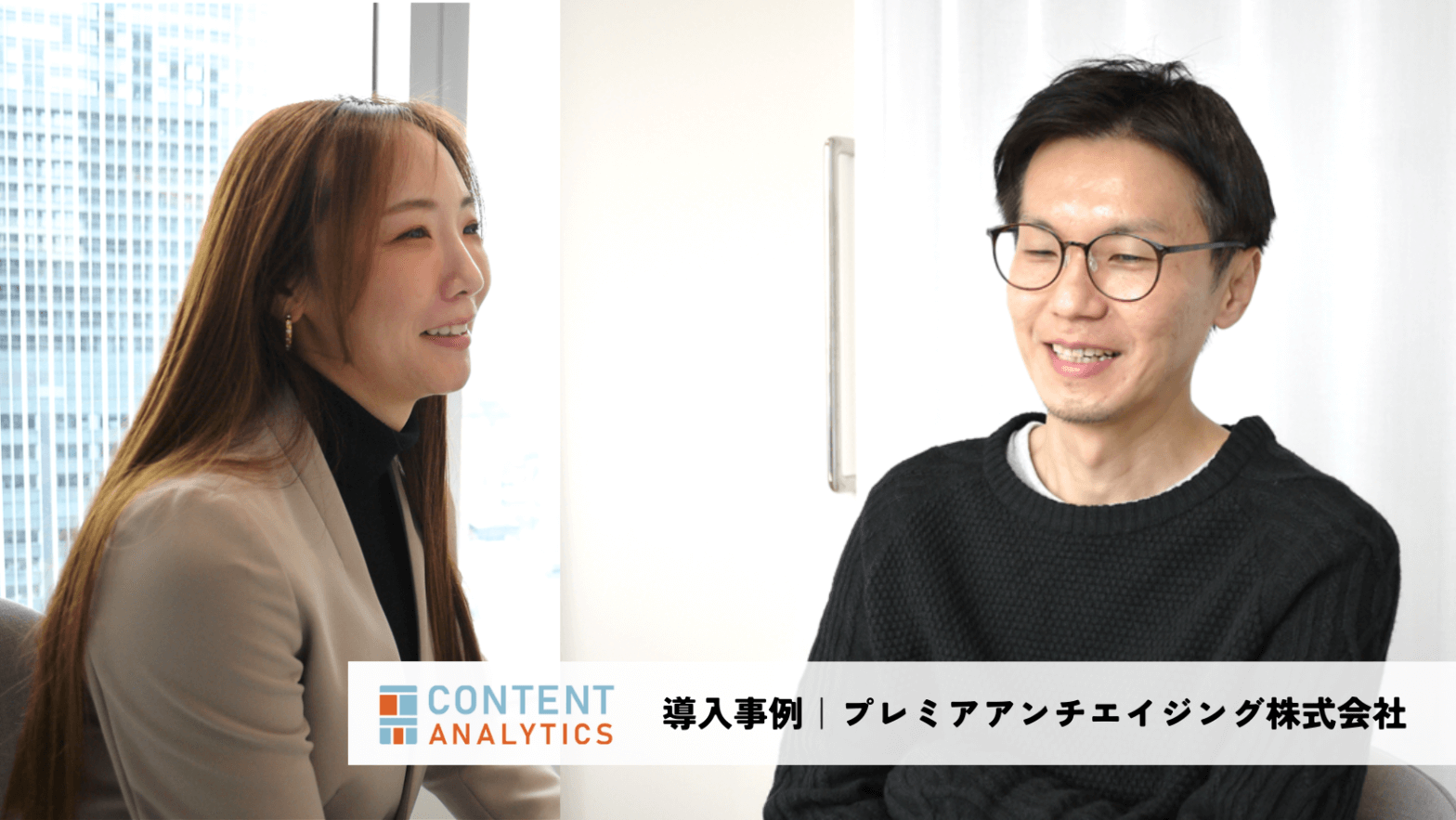
- 導入事例
- コンテンツアナリティクス導入事例|プレミアアンチエイジング株式会社様
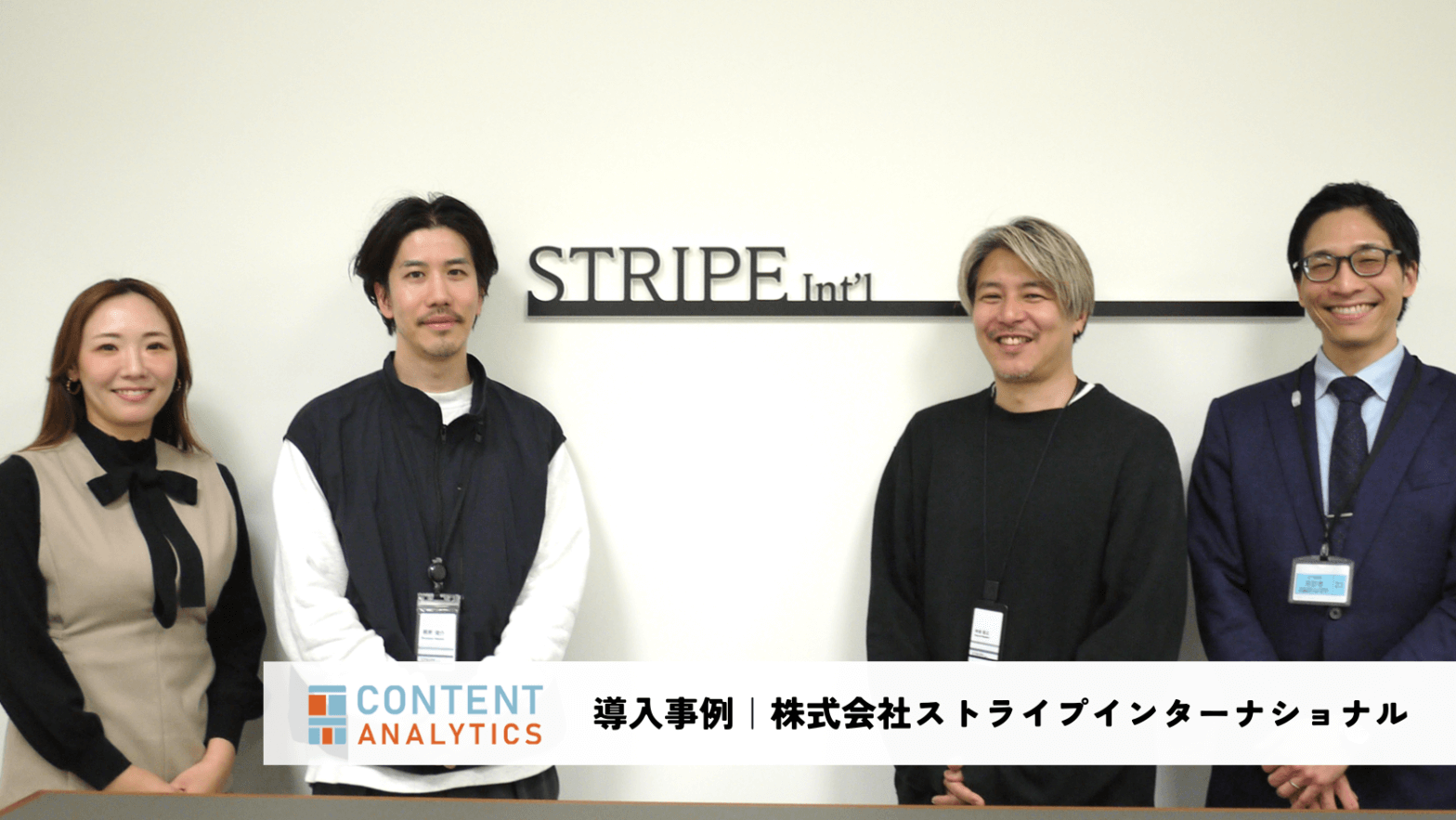
- 導入事例
- コンテンツアナリティクス導入事例|株式会社ストライプインターナショナル様
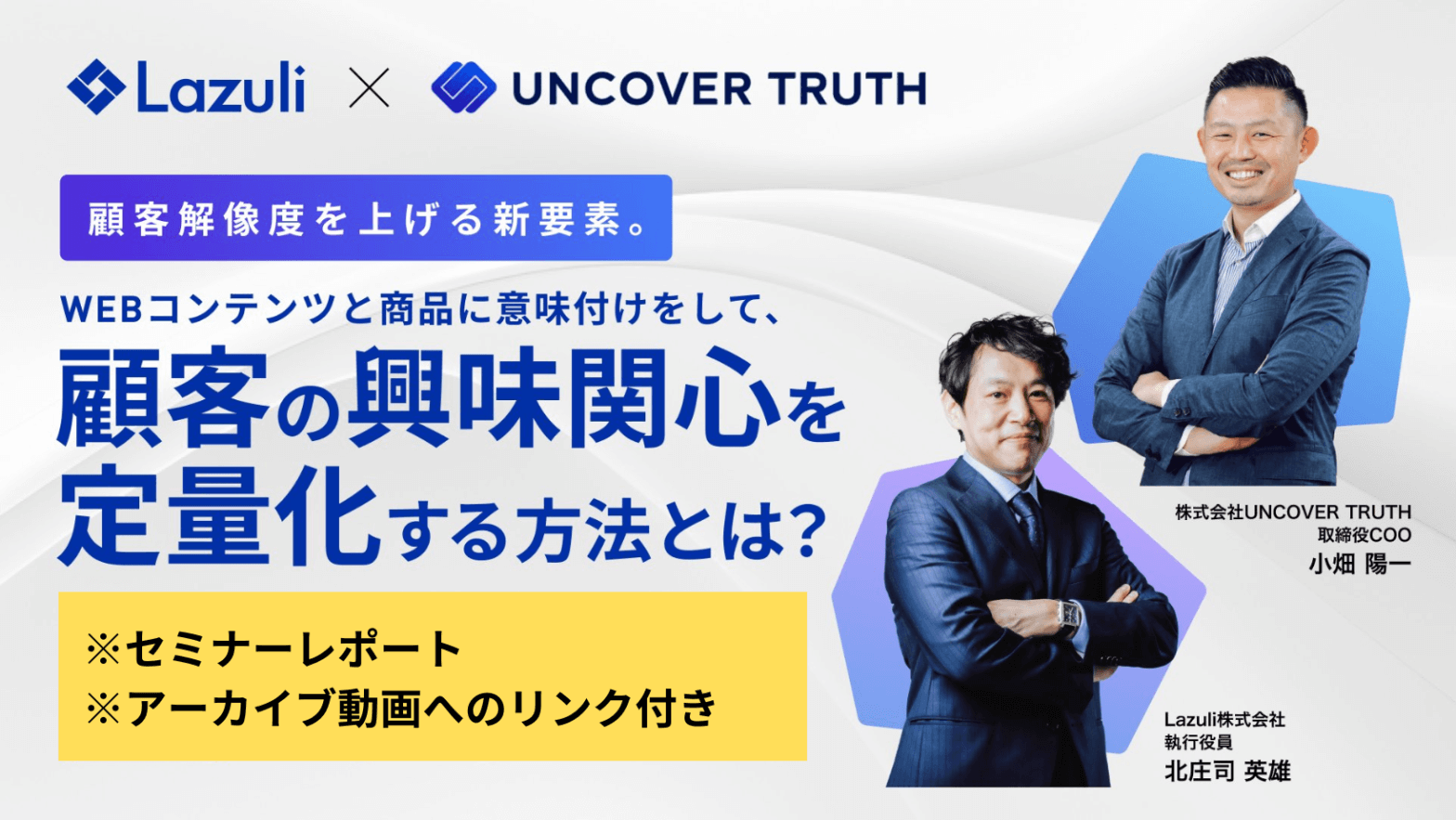
- イベントレポートカスタマーデータ活用
- 顧客解像度を上げる新要素。WEBコンテンツに意味付けをして、顧客の興味関心を定量化する方法とは?|セミナーレポート
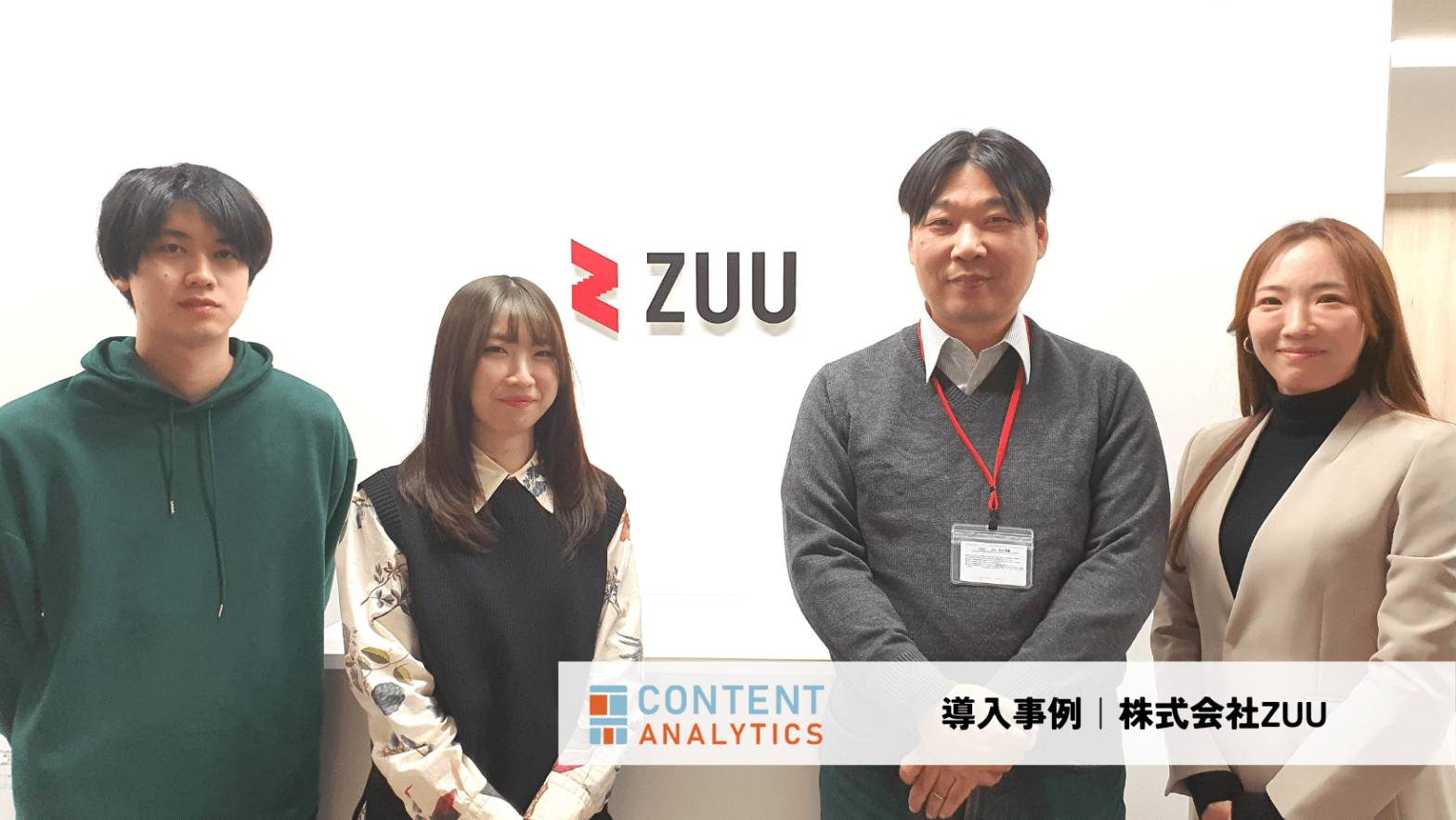
- 導入事例
- コンテンツの力を最大化!コンテンツアナリティクスを活用したCVR改善事例|株式会社ZUU様
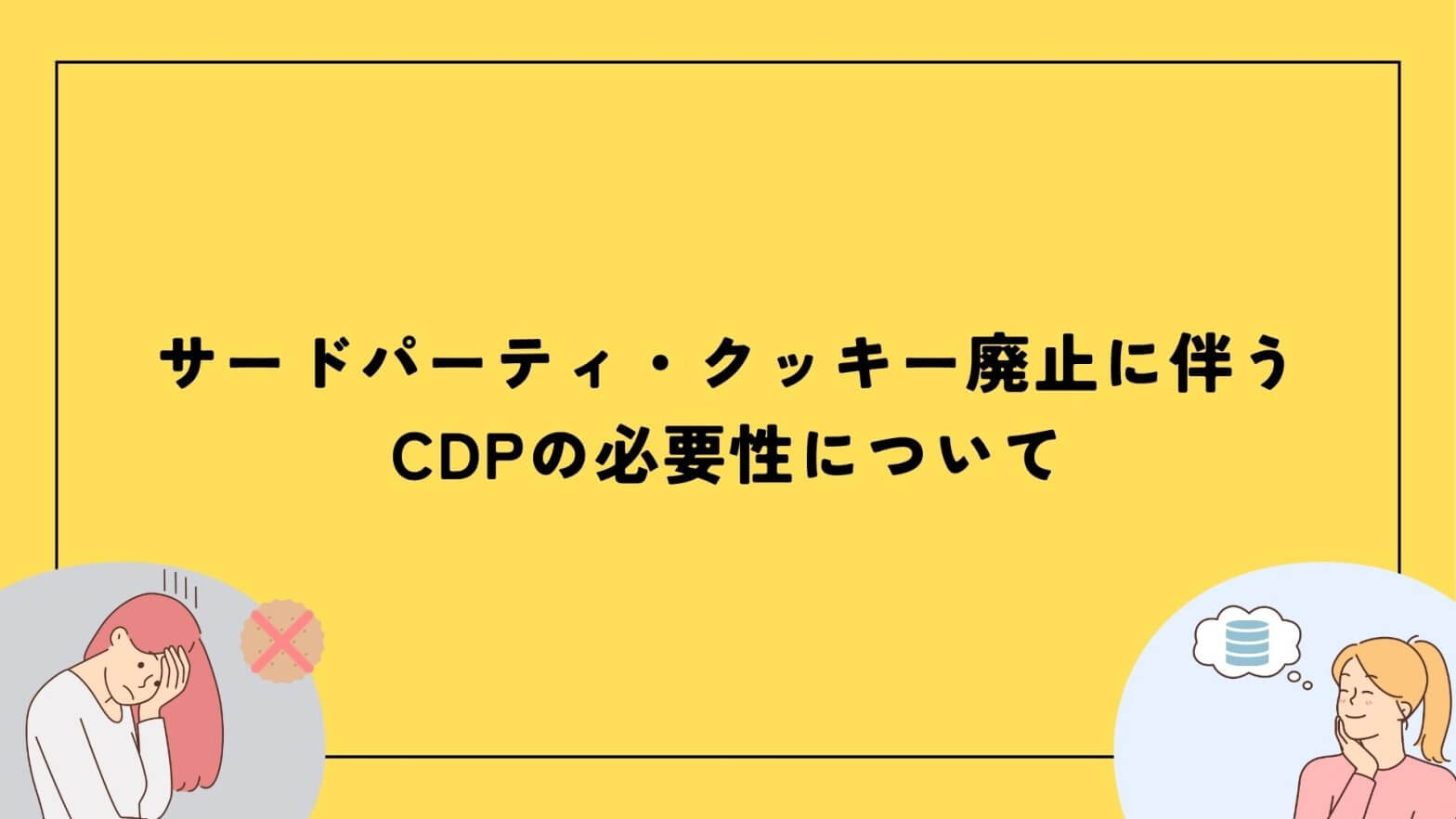
- カスタマーデータ活用
- サードパーティ・クッキー(3rd party Cookie)廃止に伴うCDPの必要性について
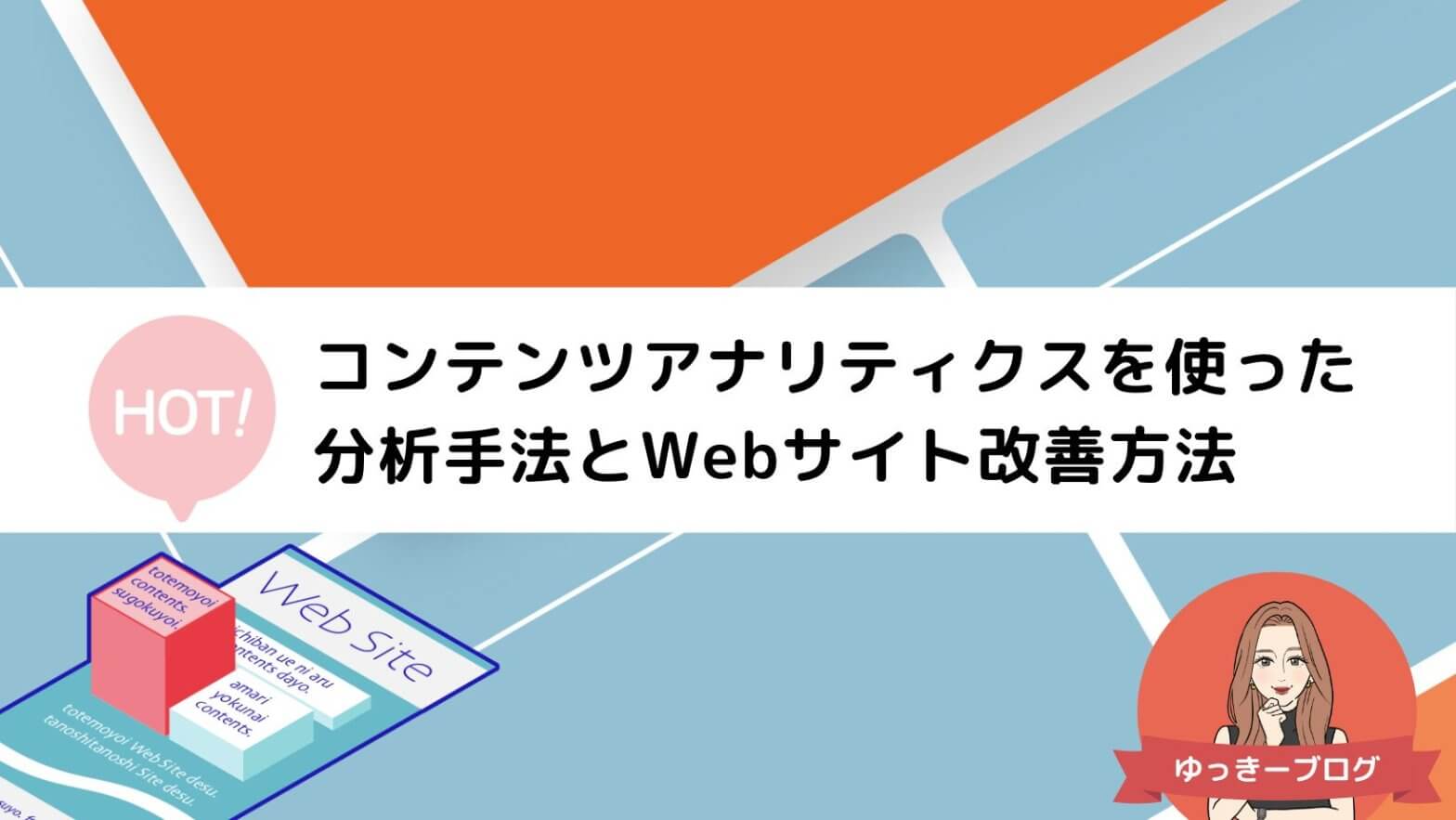
- カスタマーデータ活用
- Content Analytics(コンテンツアナリティクス)を使った分析手法とWebサイト改善方法

- イベントレポートカスタマーデータ活用
- 小川卓が解説!サイト改善のためのGA4活用。顧客の興味関心を捉えて効果を上げる次世代のUX改善手法とは?|セミナーレポート
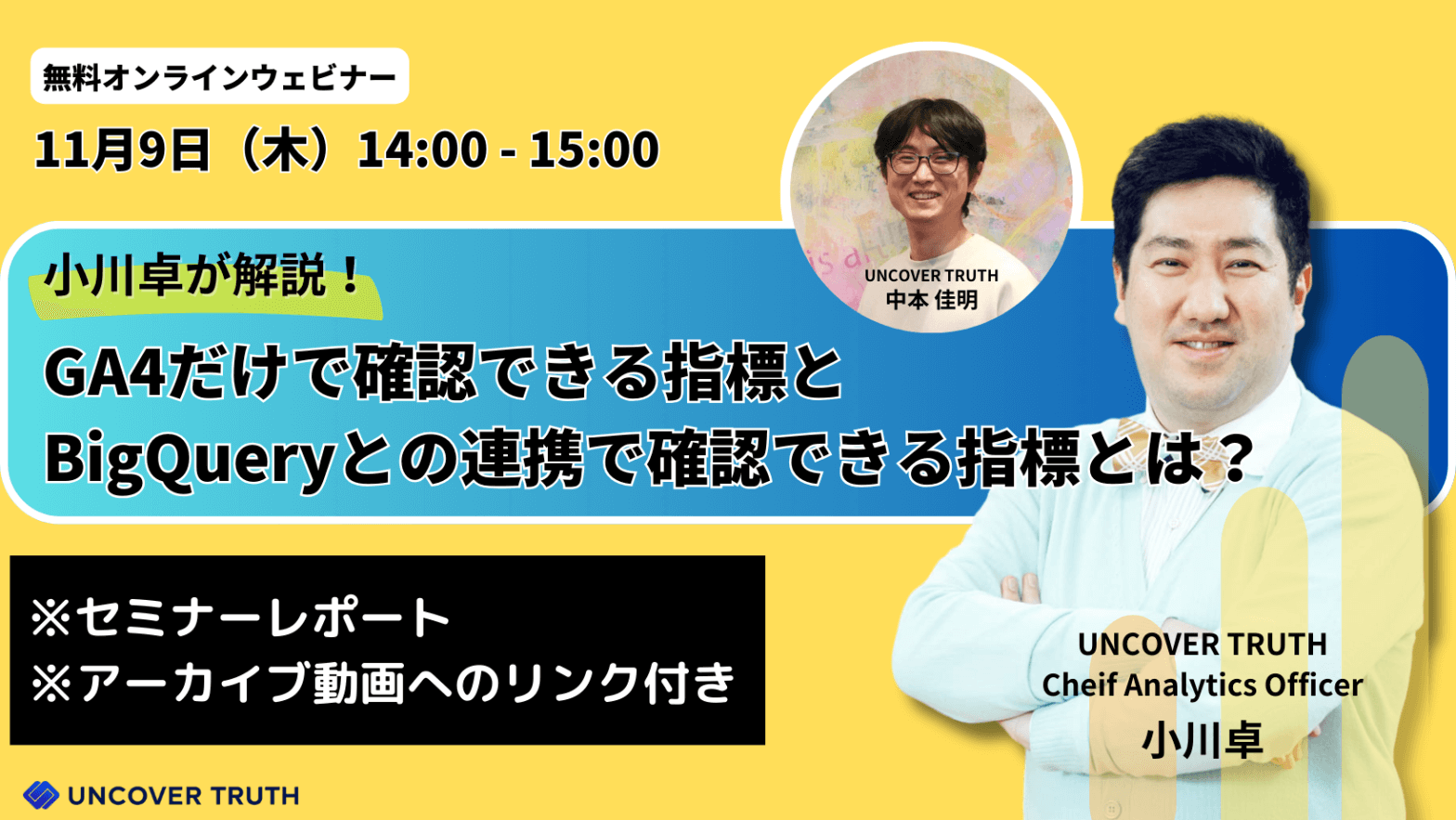
- イベントレポートカスタマーデータ活用
- 小川卓が解説!GA4だけで確認できる指標とBigQueryとの連携で確認できる指標とは|セミナーレポート

- イベントレポートカスタマーデータ活用
- 顧客体験向上のカギを握る!顧客データ活用の最適解|セミナーレポート
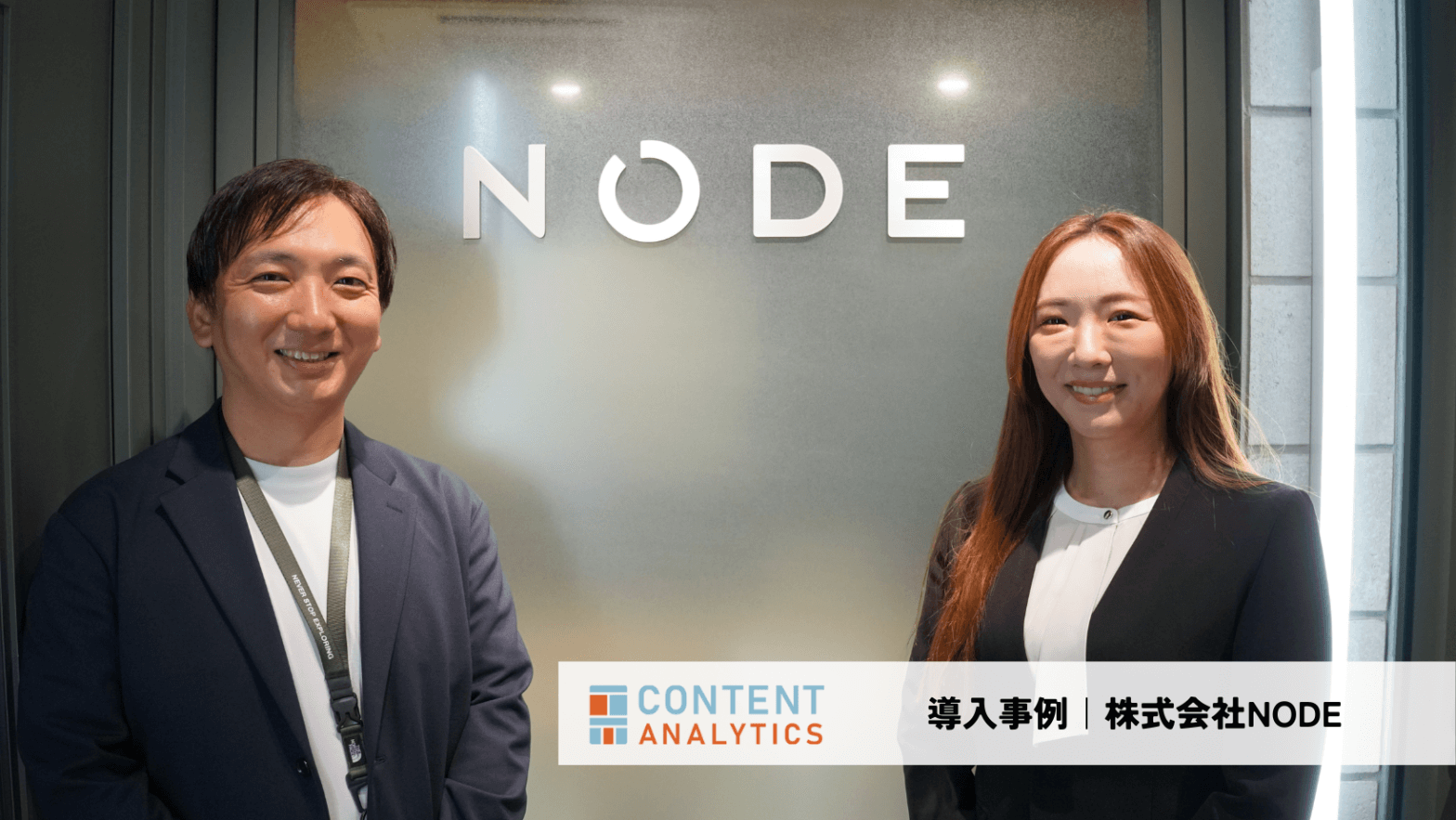
- 導入事例
- コンテンツアナリティクス導入事例|株式会社NODE様

- イベントレポートカスタマーデータ活用
- 日比谷花壇のCX改善事例に学ぶ 顧客データの”収集”と”パーソナライズ活用”とは?|セミナーレポート

- イベントレポートカスタマーデータ活用
- コメ兵のDX事例から学ぶ!経営と現場によって変わるデータ活用の考え方とは?|セミナーレポート
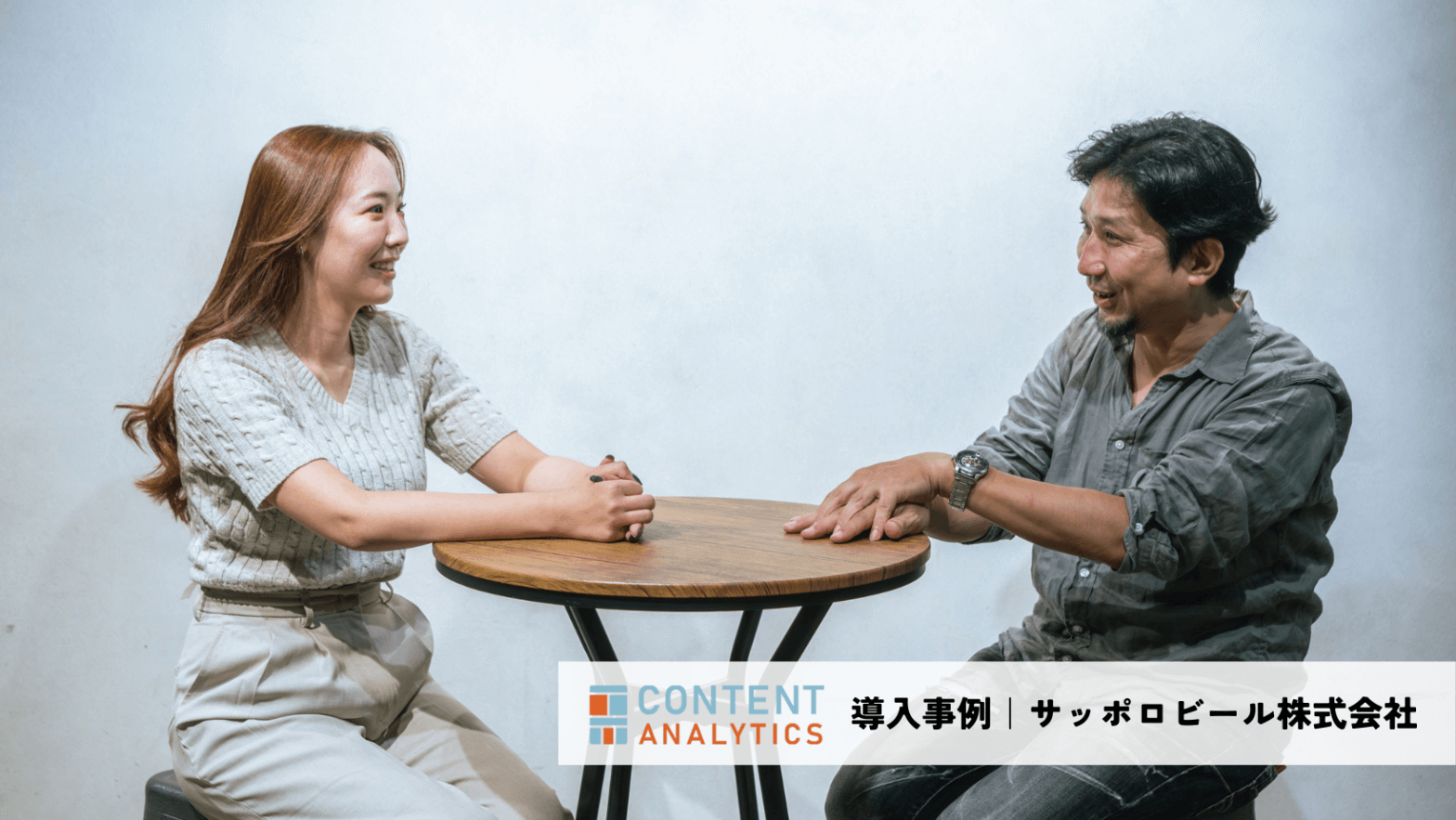
- 導入事例
- コンテンツアナリティクス導入事例|サッポロビール株式会社様


